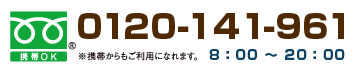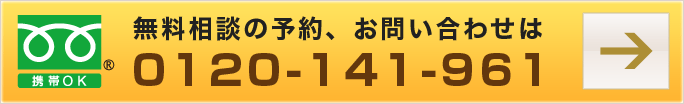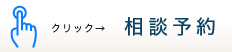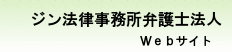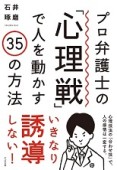破産配当に関する裁判例
裁判例紹介
破産配当に関する裁判例
破産手続の配当、物上保証人からの弁済があった場合

最高裁平成29年9月12日決定です。
破産手続の配当に関する判例です。
破産手続の配当については、破産手続開始時点での金額が基準になります。
債権者が、破産手続きに参加した後、保証人や連帯債務者等、他の債務者が一部弁済をした場合でも、債権者は、全額が弁済されない限り、破産手続開始時点での債権額を基準に配当を受けることができます。
たとえば、債権が1000万円で届出、その後に保証人から500万円の一部弁済があり、破産手続きで配当率10%の配当がされる場合、1000万円を基準に100万円をもらえることになるのです。
配当率によっては、これだと、本来の債権額を上回る金額を受け取ってしまうこともあります。
上の例で、配当率60%だと、600万円が配当されますが、保証人から500万円をもらっているので、もらいすぎですね。
このような場合、債権者は、もらいすぎになるので、それを精算しなければなりません。
その精算方法については争いがありました。
このもらいすぎの部分について、破産管財人が回収した上で、全債権者に配当しなければならないという考えもありました。この判決の原審でもそのような考えを採用したようです。
しかし、本判決では、配当に関しては、破産手続開始時点の債権額を基準として配当すればよく、後の処理は、債権者と求償権者の間の不当利得返還請求で解決すれば良いという考えに従っています。
すなわち、もらいすぎの部分については、それを支払っていた保証人等の求償権者に帰属するものと考え、破産の手続きの外で、当事者間で解決すればよいという話です。
一部弁済した保証人から債権者に請求させれば良いという考えですね。
求償権者としては、債権者に対する求償権について、破産手続きで予備的な届け出を出すこともありましたが、結局は、債権者に対する求償ができるということになるので、この予備的届け出は否定されることになります。
「破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過する部分は当該債権について配当すべきである。」