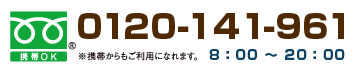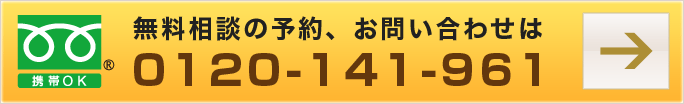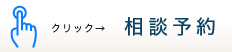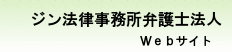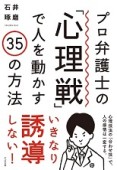FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.被災者債務整理ガイドラインの一時停止とは?
自然災害の被災者による債務整理ガイドライン手続について新型コロナウイルスに適用する特則が適用開始となっています。
2020年10月30日までの債務が対象です。
被災者の債務整理ガイドライン手続は、法人は対象外です。個人のみを対象としています。
とはいえ、法人を破産手続き、代表者の保証債務等を被災者の債務整理ガイドラインに従って整理するということがあります。そのため、当サイトでも手続の一部を解説します。
基本的な手続きについては、ジン法律事務所弁護士法人の債務整理サイトで解説しています。
今回は、返済の一時停止について解説します。
一時停止期間での追加融資
債務整理申出により一時停止の効果が生じます。
この一時停止期間中に追加融資をすることができるのか、担保設定をすることができるのかという問題があります。
すでに、ガイドラインによる債務整理手続を始め、その効果として基本的にすべての対象債権者への弁済を一時停止している以上、追加融資が必要という事態は債務整理手続全体に影響を与えることになります。
そのため、一時停止の期間中に追加融資を受ける場合は、全ての対象債権者の同意を得られた金額の範囲内、また、決められた方法で受ける必要があります。
ここに担保設定の方法も決められます。つまり、全ての対象債権者の同意を受けることで、担保設定をすることができるというわけです。
このような追加融資は、給与所得者の場合には、なかなか想定しにくい事態ですが、事業者の場合の設備資金など、事業計画との関係で必要とされるケースもあります。
一時停止前に設定した担保実行
一時停止前に、対象債権者が担保設定しているということもあります。
例えば、売掛金について担保を設定しているということもあります。
しかし、被災者による債務整理ガイドライン手続では、一時停止の期間中、対象債権者は「与信残高」を維持するものとされています。
担保として取得した売掛金であっても、その回収金を弁済に充てることは認められていません。
しかし、売掛金が回収されれば、債権者からすると担保価値が減少することになります。
そのため、変動がある取引であれば、債権者としては、代わりに別の売掛金を担保にするよう申し入れがされる可能性が高いです。
追加担保設定については、手続上も禁止されないものとされています。
一時停止違反
債務者が一時停止期間中に、勝手に資産処分をしたり、別に融資を受けて債務を負担した場合には、手続違反となります。
全ての対象債権者が同意した場合など許されるケースを覗き、勝手に資産処分をしたり債務負担したりしたことが判明した場合、対象債権者は、債務整理に異議を出せます。
この場合には、事前に登録支援専門家と協議が必要です。
この手続に異議が出されてしまうと、債務整理は終了、一時停止の効果も終了してしまいますので、くれぐれも勝手に動かないようにしましょう。
債務整理ガイドラインと代位弁済
被災者ガイドラインによる債務整理手続では、返済等も一時停止となります。
しかし、保証会社による代位弁済は進めることができるとされています。
代位弁済を進めようとする対象債権者は 保証会社等に対する適宜の情報提供その他本ガイドラインに基づく債務整理の円滑な実施のために必要な措置 を講ずるよう努めるものとされています。
保証会社に対して適切に情報提供などをしなければならないとされているのです。
代位弁済を進める場合には、事前協議の際に、他の関係者にもその予定を伝えておいたり、事前協議の場に保証会社を参加させたりする必要もあるでしょう。
債務者側で、保証会社の認識があるのであれば、登録支援専門家に申告し、今後の流れを確認してもらったほうが良いといえます。
代位弁済の場合、団体信用生命保険に影響があることが多いので、ここは注意が必要です。
調停条項案の作成
債務者、実質的には登録支援専門家だと思いますが、一時停止期間中に、債務整理のゴールである特定調停でまとめる調停条項案や関連資料を作る必要があります。
この調停条考案の提出は3か月以内(事業の再建・継続を狙う個人事業主は4か月以内)とされています。
この期限内に提出ができないという場合、対象債務者は、全ての対象債権者に対して、調停条項案の提出期限の延長が必要な理由を通知し、提出期限を3か月を超えない範囲内で延長できます。
このような延長をすると、債務整理申出から6か月以内に特定調停の申立てができないケースも出てきます。
そのような場合には、全ての対象債権者との間で合意し、6か月を超える特定の日を債務整理の終了日として定めることができるとされています。
債権者としては、期限を過ぎても調停条項案の提出がされない場合、債務者や登録支援専門家に対し、提出要請をすることになるでしょう。それでも提出されない場合には、債務整理申出から6か月を経過により債務整理手続は終了してしまいます。
法人破産と将来収入返済型の債務整理
被災者の債務整理ガイドラインでは、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある債務者は、破産手続による回収の見込みと同等以上の回収が得られる見込みを維持しつつ、それを将来にわたって分割払いとする調停条項を作成することがあります。
これは、いわゆる清算価値基準となります。財産相当額を分割して弁済することで、財産自体を維持するという方法です。
法人破産と代表者が個人再生をするような場合と同じような話となります。
代表者自身の財産を維持するため、個人再生を利用することがありますが、その場合、安定収入を得ている必要があります。代表者の就職などが必要になってくるのです。
このような収入条件を満たすのであれば、法人破産のシーンでも、代表者の債務については、債務整理ガイドラインによる解決を試みることができます。
清算価値の金額や、支払方法が合理的であるか、支払可能性があるか等は、調停条項を作成する過程で、債権者もチェックすることになるでしょう。
法人破産や代表者の被災者債務整理ガイドラインのご相談のお申し込みは以下のボタンからできます。