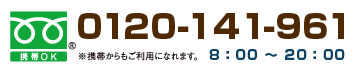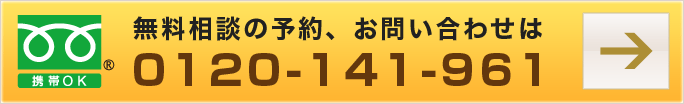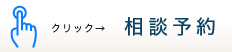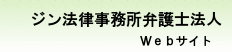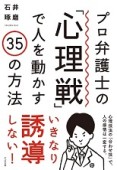FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.会社破産で請負契約はどうなる?
建設会社、不動産会社等で、請負契約の処理が問題になることも多いです。
また、請負契約をしていた相手方が倒産した場合の対応も問題になります。
破産手続きと請負契約の関係をまとめます。
会社破産と請負契約
破産した会社が当事者の請負契約があるときに、その契約がどうなるのか問題になります。
請負契約では、発注した注文者と、工事等を請け負った請負人が当事者となります。
下請けなどがあると、これが複合的になります。
請負契約の注文者の破産は?
注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、民法642条により、請負人または破産管財人は契約の解除をすることができます。
また、請負人はすでに完了した仕事の報酬や費用について、破産財団の配当を受ける形になります(民法642条1項)。
破産管財人側が契約の解除をした場合に限って、請負人は、契約の解除により生じた損害賠償請求ができます。
この場合も、請負人は、その損害賠償請求権について、破産財団の配当に加入できます(民法642条2項)。
請負人としては、自分たちに責任がないのに、注文者側の事情で、請負契約を解除されてしまうので、その不利益を損害賠償請求権として行使できるものです。
このような解除がされるのかされないのか不明な状態が続くと、契約当事者としては困るので、破産管財人または請負人は、相手方に対して、契約を解除するのか、履行するのか、一定期間を定めてハッキリするよう催告できます。
催告をしたのに、期間内に確答がないときは請負契約を解除したものとみなされます。
破産管財人が請負契約の履行を選択するには、裁判所の許可が必要です。裁判所の許可を得て履行を選択する場合には、請負人は仕事を完成させる義務を負います。
この場合、請負代金全額が財団債権となるという考え方が主流です。
破産管財人としては、請負契約を完成させてもらい、その完成物を処分したらどの程度の価格になるかという点と、請負人へ請負代金全額を払ったらいくらになるのかという点を比較して、解除するか履行するのかを決めることになります。
請負人の破産は?
請負契約の当事者で、請負人が破産手続開始決定を受けた場合、破産手続開始決定時点で履行を完了していない場合は、破産管財人は、契約の解除をし、または破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができるとされています(破産法53条1項)。
注文者破産と同じように、契約相手方である注文者は、破産管財人に対し、相当期間内に、履行するか、契約解除を選択するか確答するよう催告できます。
注文者から契約解除の主張がされることがあります。
しかし、法律上は、請負人が破産手続開始決定を受けただけでは、注文者は請負契約を当然には解除できないとされます。
管財人に対し、履行か解除か確答すべき旨の催告ができるだけです。
また、請負契約の内容に、倒産解除条項のように約定解除権の条項がある場合、これを直ちに有効と考えて良いかどうかは争いがあります。
破産管財人は、請負人が途中までやっていた工事を確認し、どの程度、未完成なのか、履行を選択することが現実的にできるのか、履行を選択した場合の費用や時間、履行を選択することが財団を増やすことになるのか等のポイントから、工事継続をするか検討します。
工事を継続しない場合は、契約の解除をすることになります。
破産管財人が、請負契約を解除した場合、破産法54条2項により、注文者は、前払金、工事の際に提供した材料部分の価額返還請求権を財団債権として行使できます。
また、損害があれば損害賠償請求権を破産債権として行使できます。
請負人が、途中まで工事をしていたときは、破産管財人は、出来高部分の報酬を注文者に請求できます。
ただ、このような請求を受けた注文者は、工事出来高査定額以上に、前払金を払っているとか、損害賠償請求権があるなどと主張してくることも多く、出来高査定が必要になってくることもあります。
多くのケースでは、このような交渉を進めたうえで、和解による解決を目指すことになるでしょう。
破産管財人は、この紛争に備えて、発注者に立会ってもらうなどして、出来高部分の確認、写真撮影等で現場状況を証拠化する必要があります。
破産管財人による履行
請負人破産で、管財人が請負契約の履行を選ぶ場合には、裁判所の許可が必要とされます。
裁判所の許可が出た場合には、請負契約の報酬は破産財団に帰属します。
管財人としては、従業員に給与を払って業務を続行してもらったり、従前の下請け業者に依頼して工事を進めることになるでしょう。
倒産事件等のご相談のお申し込みは以下のボタンからできます。