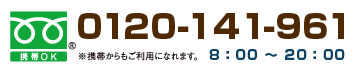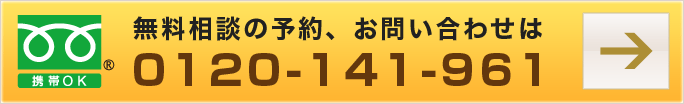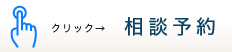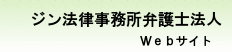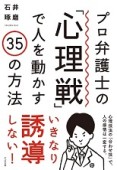FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.破産での保全処分は?
破産手続開始決定の効果の一つに、強制執行ができなくなったり、すでになされている強制執行等が失効したりするというものもあります。
これは債権者間の公平を図る趣旨です。
抜け駆けを防止する制度です。
しかし、破産の申立てから開始決定まで、相当の時聞がかかってしまう事件もあります。
申立人による資料不備や、破産管財人の選定に時間がかかることもあります。
このような場合に、破産手続き開始決定が出るまで、強制執行を止められないとすると、債権者聞の公平を害するおそれが出てきます。
そこで、各種保全処分が認められています。
保全処分が使われるケースは?
ただし、実務上は、このような危険がある場合、申立代理人が適切に説明するなどして、速やかに開始決定を出す扱いの方が多いです。保全処分を使うにしても、一定の時間がかかることから、早い段階で破産管財人を選任し、開始決定、引き継ぎを急がせるという事案の方が多いでしょう。
特殊な例として、文献等で紹介されている保全処分の使い方もあります。
これは、破産手続開始決定の時期を配慮しないといけなような場合です。
たとえば、破産会社の事業に対する行政規制があり、破産手続開始決定を受けると事業継続ができなくなるような業種の場合、すぐに破産手続き開始決定を出さずに、保全処分を出し、事業譲渡を検討することがあります。
一定の事業権について、条例等で、知事の許可等がないと譲渡できない一方で、破産手続き開始決定が出ると、その事業の許可が取り消されるようなケースでは、破産手続開始決定前に、事業譲渡が必要になります。
そのような場合、保全管理命令や保全処分で財産等の保全をした後に、破産手続開始決定を出すということもあります。
このような目的で保全処分が利用されることもあります。
それ以外には、大規模事件で、保全管理人による保全期間が必要な場合など、例外的な事件のときに限って使われる印象です。
保全処分の種類
保全処分として、強制執行等の中止命令や、複数の強制執行に対応する包括的禁止命令、弁済禁止の保全処分、否認権のための保全処分等があります。
破産申立が取り下げになったら?
このような保全処分は、破産の申立てから破産手続開始決定までに時間がかかってしまう、その間に不当な処分がされてしまうことを避ける目的で作られたものです。
そうだとすると、破産手続開始決定が出ない場合、たとえば、破産申立が取り下げられるようなケースでは、保全処分の効力を維持させる必要性はありません。
それ以外にも、取消や破産廃止によって破産手続が終了する場合にも、保全処分を残す意味はありません。
破産法では、裁判所が職権で保全措置を変更したり、取り消すことができるとしています。
また、保全処分のなかで、否認権のための保全処分の制度では、破産手続開始決定から1カ月以内に保全処分を続行しないと失効するとされています。
破産手続きが、申立ての取下げ、取消、廃止により終了になった場合には、このような規定から、保全処分は職権で取り消されたり、失効により終了することになるでしょう。
また、保全処分の登記等がある場合、保全処分を職権により取消し、これを原因として、保全処分に関する登記の抹消登記等を破産裁判所が嘱託します。
破産申立の取り下げ規制
保全処分を含めた破産手続の悪用を避けるため、保全処分がらみでは、破産申立の取り下げについても規制がされています。
保全処分だけを利用しようと考え、債務者側が保全処分が出た後に、破産申立を取り下げるという事態を避けるためです。
具体的には、強制執行等の中止命令、包括的禁止命令、破産手続開始前の保全処分、保全管理命令がされた場合、その後に、破産申立てを取り下げるには、裁判所の許可が必要とされているのです。
ここで不当な保全処分の利用、取り下げというやり方を禁じることになります。
破産手続開始決定の前の保全処分の効力は、裁判所が取下げを許可することによって理論上当然に消滅するとの考えもあります。
破産終結時の保全処分登記の取り扱いは?
破産手続終結時の保全処分登記の取り扱いについては、破産法259条2項に規定されています。
債務者の財産に属する権利で登記がされたものについて破産手続開始決定前の保全処分がなされ、
または、登記のある権利に関して否認権のための保全処分もしくは役員の財産に対する保全処分がなされたが、
これらの保全処分が効力を失った場合、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならないとしています。
破産申立てが棄却されたり、申立ての取り下げ、破産手続終結の決定、上記のとおり、否認権のための保全処分については続行されず失効した場合が、ここに含まれます。
登記申請時には、保全処分が効力を失ったことを示す書類として、取下書や、破産申立ての棄却決定、終結決定謄本等が添付されることになるでしょう。
保全処分書類の閲覧制限は?
破産法11条4項では、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書等について閲覧等の請求ができない場合を規定しています。
そのなかで、債務者以外の利害関係人は、破産法24条1項の規定による中止命令、25条2項に規定する一定の範囲に属する強制執行等又は国税滞納処分を除外した包括的禁止命令、28条1項の債務者の財産に関する保全処分、91条2項の保全管理命令、171条1項の否認権のための保全処分に関しては、破産の申立てに係る裁判までの間、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書等の閲覧請求が認められていません。
また、債務者も、一定の手続きが進むまでの期間、これらの文書等の閲覧等を請求できないとされています。
ジン法律事務所弁護士法人では法人破産の事例も豊富です。管財事件の自己破産も安心してご相談ください。
ご相談のお申し込みは以下のボタンからできます。