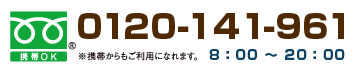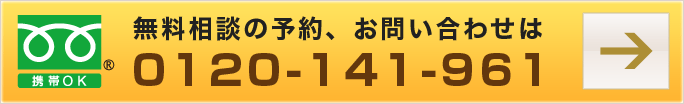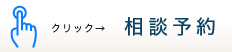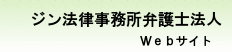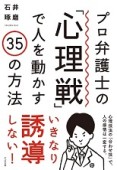FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.財団債権とは?
破産手続きの中では、一般的な貸金や売掛金よりも優先される債権があります。
そのなかで、最優先されるのが財団債権と呼ばれるものです。
財団債権とは?
破産手続きの中で、債権の取り扱いについても複数の制度があります。
そのなかでも、優先度が高い債権に財団債権と呼ばれるものがあります。
この財団債権とは何でしょうか。
財団債権は、一般債権等の破産債権よりも優先して破産手続によらず、弁済を受けられる債権です。
代表的なものとして、破産管財人の費用や一部の税金などがあります。
財団債権の特徴とは?
財団債権には優先度があります。
財団債権のなかには、破産財団の管理・換価等に関する費用などから、優先して弁済されることになっています。
さらに、その特徴として、破産手続によらずに、随時、弁済を受けられる点があります。
一般破産債権では、配当手続きなど破産手続きのなかで弁済を受けられるにとどまりますが、財団債権はいつでも弁済を受けられることになります。ただし、破産財団に限りがあれば、財団債権の優先度によって全額の弁済を受けられないことになります。
破産財団が、財団債権の総額を弁済するのに足りない場合、債権額の割合により按分弁済されます。
財団債権の優先度としては、租税債権等の優先権は認められておりません。
租税債権も新しいものが財団債権になるものの、一部は優先的破産債権になるものもあります。
財団債権は、破産手続外で行使でき、債権調査の対象にもなりませんし、免責の対象にもなりません。
債権調査の対象ではないため、存否に争いのある場合には、債権者は破産管財人を相手方に訴訟を提起して財団債権の
弁済を求めることになります。
財団債権の種類とは?
破産法上、予定されている財団債権には、次のようなものがあります。
・破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用
・破産財団の管理、換価および配当に関する費用。管財人の事務費や報酬もここに含まれるとされます。
・破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権で、破産手続開始時点で、納期限の未到来または納期限から1年を経過していない税金等(加算税を除く)
・破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
・事務管理・不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
・ 委任の終了または代理権消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
・破産法53条1項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権。未履行の請負契約で注文者破産の場合に、請負人が仕事を完成して目的物を引き渡した場合の請負代金請求権が例としてあげられます。 ・破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れがあった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの聞に生じた請求権
その他に以下のような債権も財団債権とされています
・ 双務契約が解除された場合の相手方の価額返還請求権
・ 継続的給付における破産申立て後の給付に係る請求権
・ 債権者委員会の費用請求権
・ 使用人の給料等
破産管財人がした行為によって生じた請求権
財団債権のうち、破産財団に関し管財人がした行為によって生じた請求権(148条1項4号)とは何でしょうか。
破産管財人が契約等をした場合の相手方に生じた請求権、破産管財人の不法行為により被害者に生じた損害賠償請求権等がと言われます。
不作為でも、行為とされます。
不作為の例として、建物が破産財団のような場合で、土地の不法占拠状態になってしまっているような場合、破産手続開始決定後の占有は、破産管財人による不法占有として、損害賠償請求権が財団債権となる例があります。
双務契約の履行を選択した場合の相手の権利も財団債権になります。
破産管財人が破産法53条1項で、債務の履行を選択した場合、破産管財人は相手方に履行の請求をします。
相手方の請求権は財団債権となります。
そのため、履行するかどうかの選択については、破産財団にとって解除を選択したほうがプラスになるか比較検討することになります。
なお、100万円を超える価額の場合、双方未履行の双務契約の履行も裁判所の許可が必要です。
光熱費関係の財団債権は?
電気、水道、ガス等の光熱費のように、継続的給付を目的とする双務契約の場合も注意が必要です。
契約相手方が、破産手続開始申立後開始前にした給付の請求権も財団債権になります。
1ヶ月単位のように、代金を、一定期間で算定する場合には、申立日の属する期間分の全部を含むことになります。
なお、個人の自宅建物で利用している電気、水道、ガス等の料金は、破産者負担となります。
財団債権の弁済時期
財団債権は、随時支払うことができるとされていますが、財団の金額がいくらになりそうか、全体が見えない段階では支払いにくいことが多いです。
また、金額について、100万円以下の財団債権の承認は、裁判所の許可が不要とされています。
ただ、支払内容等は、収支計算書に記載するなどして報告します。
滞納税金と財団債権
財団債権のなかで多くの割合を占める、税金や社会保険料など公租公課があります。
このような税金でも、現在は、一律財団債権になるのでなく、財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権に分かれます。
財団債権として扱われる公租公課は次のようなものです。
・破産手続開始前の原因に基づいて生じた公租公課のうち、破産手続開始当時、具体的納期限が未到来または具体的納期限から1年を経過していないもの
・破産財団に関して、破産手続開始後の原因に基づいて生じる公租公課のうち、破産財産の管理、換価に関する費用に該当するもの(他の財団債権にも優先)
・納期後の上記の公租公課に係る延滞税等
これに対し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた公租公課のうち、破産手続開始当時、納期限から1年以上経過しているもの等は優先的破産債権とされます。
さらに、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生じる公租公課のうち、破産財産の管理、換価に関する費用に該当しないもの等は、劣後的破産債権になります。
公租公課支払の優先順位は?
財団債権を全額払える余力がない場合、財団債権の公租公課は、原則として、按分弁済になります。
すべてが同順位で、金額によって配当する形です。
これに対し、優先的破産債権の公租公課を一部だけ支払う場合は、優先的破産債権間の優先順位は、民法、商法その他の法律の定めるところによることになっています。
こちらは按分弁済ではなく、優先順位があることになります。
優先順位は、①公租(国税、地方税)、②公課(社会保険料、下水道料金等)、③私債権(優先的破産債権に該当する労働債権等)の順です。
国税と地方税との聞では優先劣後の関係はありません。
同順位の優先的破産債権を全額払えないときは、同一順以内では、按分して配当します。
たとえば、配当できる原資が、優先的破産債権の中で、①税金の合計額を超えるものの、②社会保険料等(公課)までは足りない場合、公租(国税および地方税)を全額支払ったうえで、第2順位の社会保険料(公課)等に按分して配当するのです。
税金の差押滞納処分と破産手続開始決定
破産手続開始決定と国税滞納処分の関係については、破産手続開始決定後は、滞納処分はできないとされています。
これに対し、破産手続開始決定前に、破産財団に対してすでになされた滞納処分は、開始決定が出たからといって続行は妨げないとされています。
租税債権が財団債権か優先的破産債権かを問わず、区別はされていません。
財団債権内の優先順位は?
破産財団が、財団債権の総額を弁済できないときは、債権額の割合によって按分弁済されます。
ただし、財団債権には優先順位があります。同順位の財団債権の場合には、按分弁済されますが、管財人報酬等の優先順位が高いものは先に払われます。
1 管財人報酬(事務費、費用も)
2 債権者申立て又は第三者申立ての場合の予納金補填分
3 148条1項1号及び2号のうち、上記を除いたもの
(破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権)
(破産財団の管理,換価及び配当に関する費用の請求権)
4 その他の財団債権
という順位です。
4番めの「その他の財団債権」には、租税債権の財団債権部分、労働債権の財団債権部分も入ります。
両者は同列です。優先的破産債権の場合の順位とは変わっています。
また、破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権(破産法148条1項4号)や破産法53条1項に基づいて破産管財人が履行選択した場合の相手方の請求権(148条1項7号)等も同列扱いとなります。
固定資産税は、年度によって変わります。
破産手続開始の年度の固定資産税は148条1項3号の財団債権です。
破産手続開始決定の翌年の1月1日になると、翌年度の固定資産税は148条1項2号の財団債権となります。
優先順位3位になります。
同じ固定資産税でも優先順位が異なる結論になるのです。
ジン法律事務所弁護士法人では破産管財事件の事例も豊富です。管財事件の自己破産も安心してご相談ください。
ご相談のお申し込みは以下のボタンからできます。